CPUとGPUの違いを解説!情報システム部門のための戦略的選択ガイド
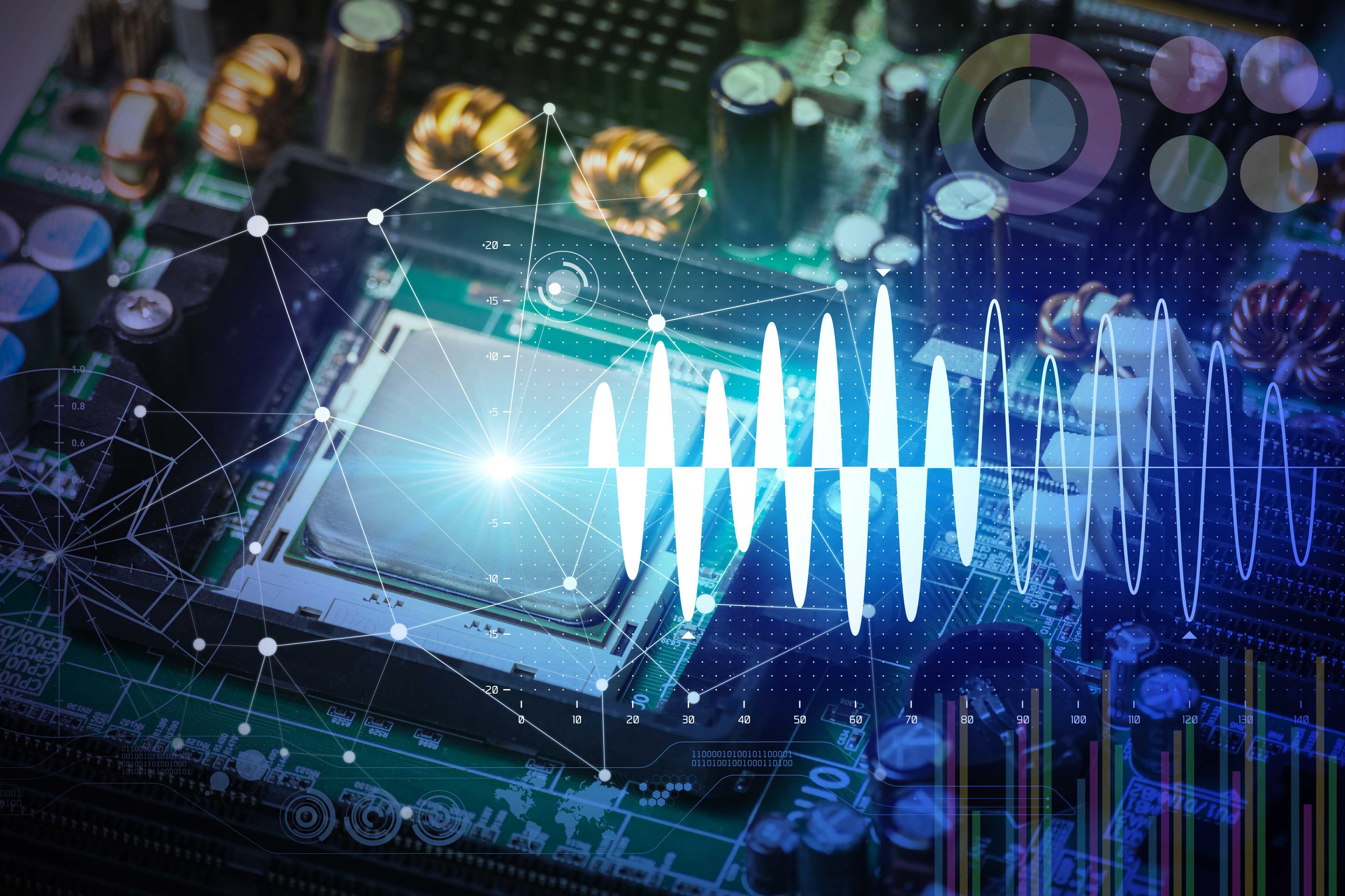
課題解決のためのノウハウ
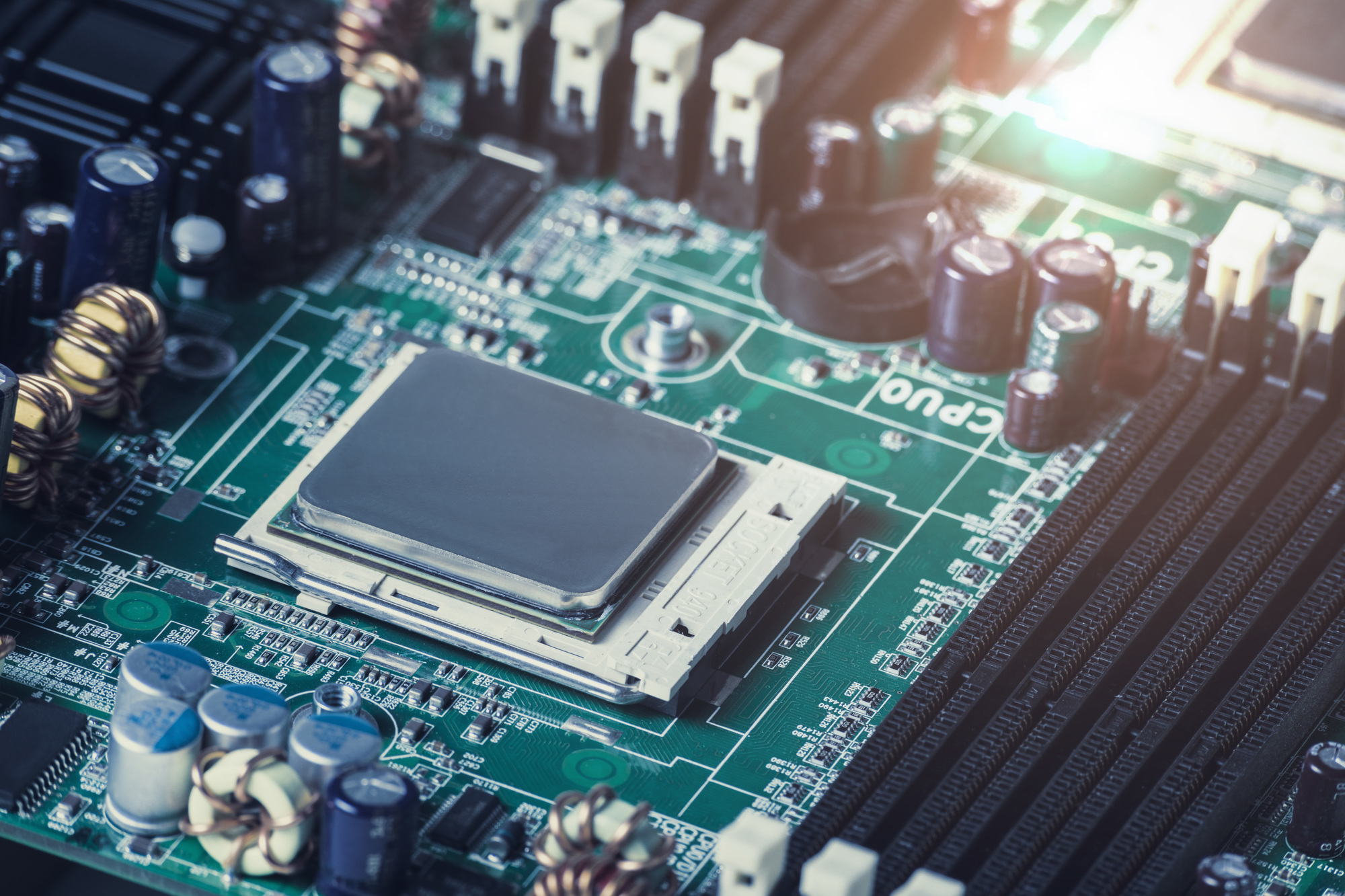
生成AIブームにより、GPUサーバーの消費電力が急激に増加しています。従来のサーバーと比較して高性能GPUサーバーは大幅に多くの電力を必要とし、データセンターの電力密度が従来の1ラック数kVAから20kVA超へと劇的に変化しました。AI処理の高度化に伴い、空冷方式の限界を超えた液体冷却技術の導入が不可欠となっています。本記事では、GPUサーバーの消費電力問題から最新の冷却技術、適切なデータセンターの選定方法まで解説します。
GPUサーバーの急速な普及により、データセンターの電力環境は根本的な変革を迫られています。従来のインフラでは対応困難な高消費電力環境の実態と、それに伴う課題について見ていきます。
AIワークロードの増加に伴い、サーバー用プロセッサの消費電力が年々増加しています。高性能化と引き換えに、CPUとGPUの消費電力が大幅に上昇する傾向が続いており、従来のサーバーインフラでは対応困難な状況となっています。これらの高消費電力プロセッサを複数搭載したサーバーでは、システム全体で数kWから10kW超の消費電力となり、従来のCPUサーバーとは次元の異なる電力需要が生まれています。
このような高性能AIワークロードの増加により、データセンターの電力インフラは根本的な見直しが必要となっています。特に機械学習や深層学習処理では、大量の並列計算を長時間継続するため、従来想定していた電力使用パターンを大きく上回る消費電力が発生しています。
一般的なデータセンターの電力容量は1ラック当たり2~8kVA程度でしたが、高性能GPUサーバーには20kVA程度が必要となっています。高性能GPUサーバーは1台で数kWから10kW超の電力を消費し、従来のサーバーとは桁違いの電力要求となります。このため企業は新たな設置場所の検討を余儀なくされています。
電力密度の急激な増加は、単に電力供給能力の問題だけでなく、配電設備の増強や電源設備の大型化も必要とし、データセンター全体の設計思想を根本から見直さなければならない状況を生み出しています。
データセンターの基本的な仕組みや役割について詳しく知りたい方は、「データセンターとは?基礎知識からクラウドとの比較、導入メリットまで徹底解説」も併せてご覧ください。
生成AIの学習処理には従来の数十倍から数百倍の計算能力が必要となり、膨大な並列処理を担うGPUの需要が急増しています。ChatGPTのような大規模言語モデルでは数千から数万枚のGPUを同時稼働させ、データセンター全体で膨大な電力を消費します。データセンターの電力消費量は急速に増加しており、電力インフラの強化と効率化が急務となっています。
特に大規模な生成AIサービスでは、推論処理だけでなく継続的な学習処理も並行して実行するため、24時間365日の高電力消費が継続する特殊な運用環境となっています。
GPUサーバーについて知りたい方は、「GPUサーバーとは?GPUサーバーのメリットや高密度サーバーのデータセンター運用のポイントを解説」も併せてご覧ください。
高消費電力GPUサーバーの安定稼働には、従来の空冷方式を超えた革新的な冷却技術が不可欠です。液体冷却を中心とした最新技術について解説します。
従来の空冷方式では、1ラック当たり20kWの冷却が限界とされています。高性能GPUサーバーの消費電力がこの限界値に近づいているため、空冷方式では冷却能力が不足する状況です。冷却不足は性能低下や故障につながるため、根本的な冷却方式の変更が求められています。発熱量の増加に対して、従来のファンベースの冷却システムでは物理的な限界があり、新たな冷却アプローチが必要となっています。
空冷方式の場合、ファンの回転速度を上げることで冷却能力を向上させようとしますが、騒音レベルの増加や消費電力の増大という副作用も生じ、総合的な効率改善には限界があることが明らかになっています。
液体冷却技術には複数の方式があり、それぞれ異なる特徴と適用場面を持っています。GPUサーバーの高発熱に対応する各冷却方式の特徴について解説します。
冷媒をCPUやGPUに直接循環させて熱を除去する方式で、空気の約20倍の熱伝導率を活用した効率的な冷却を実現します。プロセッサに直接接触する冷却プレートを通じて熱交換を行うため、最も効率的な熱除去が可能となります。
サーバーラック背面に水冷装置を設置する方式で、空冷式サーバーでも利用できる利点があり、既存インフラとの親和性が高い特徴があります。既存のサーバー構成を大幅に変更することなく導入できるため、段階的な移行が可能な現実的なソリューションとして注目されています。
絶縁性液体にサーバー全体を浸す最も効率的な手法で、従来では実現困難な高密度実装と省エネ化を両立できる革新的な技術です。サーバー全体が液体に浸かることで、すべての発熱コンポーネントを均一に冷却でき、従来の冷却方式では達成困難な超高密度実装を可能にします。
液冷システムにより従来の空冷方式と比較して冷却効率の大幅な向上が可能となります。大手通信事業者N社の実証実験では、約20度の水を循環させる液冷方式で電力使用効率(PUE値)の大幅改善を確認しています。また、大手IT企業のF社では、沸騰冷却技術により冷却性能を従来の2倍に向上させ、環境負荷低減と安全性確保を両立したソリューションを提供しています。一方で、水漏れリスクや初期投資コスト、専門技術者による保守運用などの実装課題への対策が必要となります。
特に液体冷却システムの導入には、従来の空冷システムとは異なる専門知識と保守体制が必要となるため、運用担当者の教育や緊急時対応手順の整備が重要な課題となっています。
GPUサーバーの安定稼働には、従来とは異なる要件を満たすデータセンターの選定が欠かせません。技術面と運用面から評価すべき具体的なポイントを解説します。
電力容量については20kVA以上の電力供給が可能なデータセンターを選択する必要があります。冷却性能では1ラック20kW超の発熱に対応できる液冷対応設備が判断基準となります。立地条件として寒冷地を活用したナチュラルクーリングも考慮要素です。
冗長性については電力設備とネットワーク機器の二重化構成による安定運用確保が必要です。また、将来的な拡張性も重要な選定要素となり、追加のGPUサーバー導入やシステム拡張に対応できる余裕のある電力容量と冷却能力を備えたデータセンターを選択することが求められます。
サーバーラックの規格や構成について詳しく知りたい方は、「データセンターのサーバーラックの規格とは?種類や選び方を解説」も併せてご覧ください。
オンプレミス型とクラウド型の選択では、長期的なランニングコストと管理工数を総合的に評価することが大切です。オンプレミス型は初期投資が大きいものの運用コストを抑制でき、大容量データ処理では有利です。電力監視にはデータセンターインフラ管理(DCIM)ツールやインテリジェントPDU(電力分配装置)を活用し、リアルタイムでの消費電力可視化と最適化を実現できます。
特にGPUサーバーの場合、処理負荷に応じて消費電力が大きく変動するため、動的な電力管理と負荷分散が重要な運用要素となります。また、メンテナンス計画においても、高発熱コンポーネントの定期的な清掃や冷却システムの点検頻度を従来のサーバーよりも高める必要があります。
省エネルギー対策では、政府が設定したベンチマーク目標への対応が重要です。資源エネルギー庁は2030年までにデータセンター業界でPUE値1.4以下の達成を目標として設定しており、一定規模以上の事業者には報告義務が課されています。
こうした目標達成に向けて、GPUサーバー運用においても様々な省エネ手法の導入が進んでいます。GPU電力制限設定により、性能要件に応じた消費電力の最適化が可能です。最新世代GPUでは製造プロセス微細化により同一性能でも消費電力を削減できます。PUE値1.4達成には液冷システムと外気冷房の組み合わせが有効です。さらに、AIワークロードの特性を活用した電力管理により、学習処理と推論処理の電力要求の違いを考慮した動的な電力配分も重要な省エネ手法となります。
将来的には、再生可能エネルギーとの組み合わせや、余熱回収システムの導入により、さらなる環境負荷低減が期待されています。
参考:データセンター業のベンチマーク制度 制度の概要|資源エネルギー庁
データセンターの省エネ技術とグリーン化について詳しく知りたい方は、「グリーンデータセンターとは?生成AI時代に必須の省エネ技術」も併せてご覧ください。
GPUサーバーの消費電力問題は、生成AI時代のデータセンター運用の最大の課題となっています。AIワークロードの高度化に伴う消費電力急増により、従来の空冷方式では冷却が追いつかない状況への対処が急務です。液体冷却技術の導入により冷却効率の大幅向上と高密度実装の両立が可能となり、特に直接液体冷却と液浸冷却が注目されています。データセンター選定では20kVA以上の電力供給と液冷対応設備、立地条件を総合評価し、運用面ではオンプレミス型とクラウド型の特性を活かしたハイブリッド構成が効果的です。今後のGPUサーバー導入では、消費電力最適化と冷却技術の革新により、持続可能で高効率なIT基盤の構築が企業競争力の決定要因となるでしょう。
こうしたGPUサーバーの高電力要求に対応するデータセンターの選定には、十分な電力容量と高効率な冷却システムが不可欠です。STNetのデータセンター「Powerico(パワリコ)」は、1ラックに機器定格21kVAまでの電力供給が可能で、高密度GPUサーバーにも対応できる電力容量を備えています。高効率な空調システムによる最適な冷却環境と24時間365日の専門技術員による監視体制により、安定したGPUサーバー運用を実現します。GPUサーバーの導入やデータセンター選定でお悩みの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。