サイバーセキュリティとは?サイバー攻撃を受けた際のリスクや対策を解説

課題解決のためのノウハウ
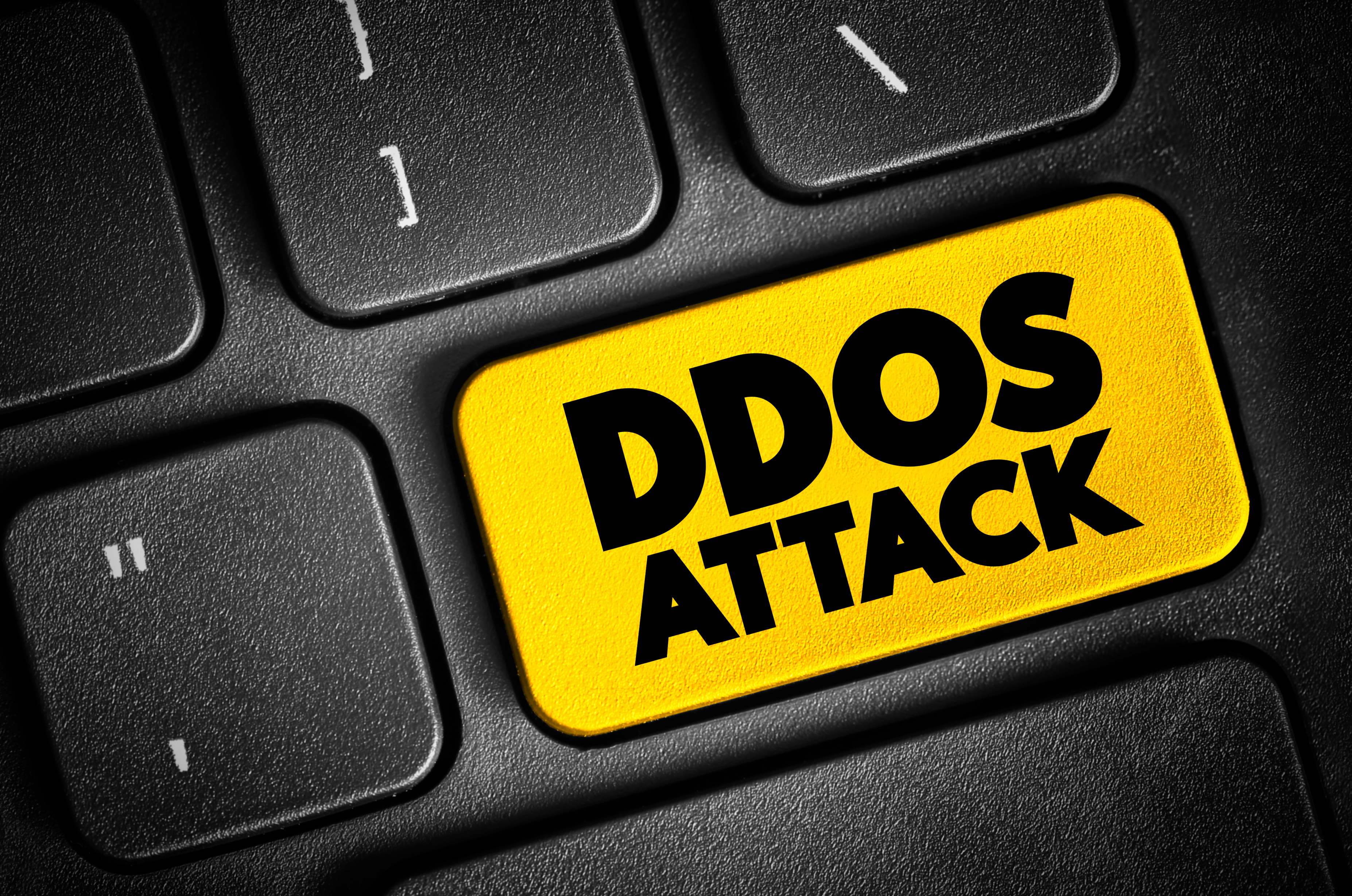
DDoS攻撃は年々巧妙化し、企業にとって深刻な脅威となっています。IoTを利用した大規模攻撃や5G時代の新たなリスクなど、従来の対策では対応しきれない課題が浮上しています。本記事では、最新のDDoS攻撃の動向を踏まえ、企業が取るべき包括的な対策を詳しく解説します。技術的な防御手段から組織全体で取り組むべきポイント、投資対効果の考え方まで、幅広い視点でDDoS対策の重要な側面を探ります。サイバーセキュリティの強化に関心のある企業担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
DDoS攻撃の全容を理解することは、効果的な対策の第一歩となります。
DDoS攻撃(Distributed Denial of Service attack)は、複数の攻撃元から大量のトラフィックを標的に集中させ、サービスを機能不全に陥らせる手法です。DoS攻撃が単一の攻撃元から行われるのに対し、DDoS攻撃は分散型であるため、規模が大きく、防御が困難となります。攻撃者は多数の感染端末(ボットネット)を利用し、標的のサーバーやネットワークリソースを枯渇させることで、正規ユーザーのアクセスを妨害します。
DDoS攻撃は、主にネットワーク帯域消費型攻撃とサーバーリソース消費型攻撃の二つに分類されます。
この攻撃は、大量のパケットを送信してネットワークの帯域幅を消費します。主に以下のような攻撃手法があります。
| 攻撃例 | 攻撃内容 |
|---|---|
| UDP Flood | 大量のUDPパケット(インターネット上でデータを送受信する際の小さな情報の塊)を送信し、帯域幅を消費する |
| ICMP Flood(Ping Flood) | 大量のICMP(Internet Control Message Protocol)エコーリクエストでもPingを送信してネットワークを圧迫させる |
この攻撃は、サーバーのリソースを枯渇させることを目的とします。主な攻撃手法には以下があります。
| 攻撃例 | 攻撃内容 |
|---|---|
| SYN Flood | TCP接続(Webサイトの閲覧などで使用される通信方式)の確立処理を悪用し、大量のSYNパケット(接続要求)をターゲットサーバーに送ることで、サーバーは未完了の接続を保持しつづけるため、サーバーリソースを枯渇させる |
| ACK Flood | 大量のACKパケット(データ受信の確認応答に使用される通信パケット)を送信し、サーバーやネットワークの処理能力を低下させる |
| HTTP Flood/HTTPS Flood | 大量のHTTPまたはHPPTSリクエスト(Webサイトにアクセスする際の要求)でWebサーバーに負荷をかける |
| Slow HTTP Attack | HTTPリクエストを故意に遅延させ、サーバーリソースを占有する |
攻撃者は、これらの手法を組み合わせて多層的な攻撃を仕掛けることがあり、防御をより困難にしています。
IoTデバイスの普及に伴い、Mirai等のIoTマルウェアを悪用した大規模ボットネットによるDDoS攻撃が増加しています。さらに、5Gの普及により、攻撃の規模と複雑さが増大すると予測されており、新たな対策の必要性が高まっています。
DDoS攻撃をはじめとした、さまざまなサイバー攻撃のリスクや対策について詳しくは、「サイバーセキュリティとは?サイバー攻撃を受けた際のリスクや対策を解説」をご覧ください。
DDoS攻撃は企業に深刻な影響を及ぼし、その被害は金銭的損失にとどまりません。
DDoS攻撃は、企業のオンラインサービスを停止させ、収益損失、顧客満足度の低下、ブランド価値の毀損など、多岐にわたる影響をもたらします。サービス停止時間が長引くほど、損害は拡大し、顧客離れや取引先との信頼関係の崩壊につながる可能性があります。さらに、DDoS攻撃が他のサイバー攻撃の前触れや隠れみのとして利用されることも少なくありません。結果として、データ漏洩やシステム侵害など、より深刻な被害に発展するケースもあります。
2015年、東京五輪・パラリンピック大会組織委員会がDDoS攻撃の標的となりました。サーバーに大量のアクセスが集中し、ホームページの機能停止に追い込まれました。さらに、2021年の大会期間中には、公式サイトなどで検知した攻撃回数はおよそ4.5億回に達しました。この事例は、大規模イベントがDDoS攻撃の標的となりやすいこと、そして長期にわたって攻撃が継続する可能性があることを示しています。
2024年パリ五輪では、大会開催前後にさまざまなサイバー攻撃が発生しました。特に注目されたのは、ハッカーグループによる一連のDDoS攻撃です。これらのグループは、オリンピックのスポンサー企業や関連組織を標的としました。
また、イスラエルのオリンピック関連組織や、フランスの自治体組織もDDoS攻撃の標的となりました。これらの攻撃は、政治的な動機や抗議活動の一環として行われ、大規模なスポーツイベントがサイバー攻撃の主要な標的となることを改めて示しました。
これらの事例は、DDoS攻撃が単なる技術的な問題にとどまらず、国際的なイベントや企業の評判、さらには外交関係にまで影響を及ぼす可能性があることを示しています。企業や組織は、こうした複雑な背景を持つ攻撃に対して、技術面だけでなく、組織的かつ戦略的な対応が求められています。
サイバー攻撃の現状、その影響について詳しくは、お役立ち資料「サイバー攻撃の現状と企業が知るべきリスク」をダウンロードしてご覧ください。
DDoS攻撃から企業を守るためには、多層的かつ包括的なアプローチが不可欠です。ここでは主要な対策を紹介します。
ファイアウォールの適切な設定やIPアドレスフィルタリング、地理的制限などの基本的なアクセス制御を実施します。ただし、これだけでは高度なDDoS攻撃を完全に防ぐことは困難です。
トラフィックの異常を検知し、自動的に緩和措置を講じる機能を備えた、高度なツールを導入します。機械学習やAIを活用して、正常なトラフィック(通常の通信)と攻撃トラフィック(悪意のある通信)を高精度で識別し、リアルタイムで対応します。
ネットワーク層からアプリケーション層まで、複数の層で防御策を講じます。
上記のようなセキュリティ技術を組み合わせることで、多様な攻撃に対応します。
ロードバランサの技術について詳しくは、「企業のIT基盤を強化するロードバランシング戦略を解説」をご覧ください。
大規模な攻撃にも柔軟に対応できる、クラウドベースのDDoS対策サービスを活用します。クラウドベースのため、物理的な機器を必要とせず、環境を選ばずに簡単に導入できることが特長です。優れたネットワーク処理能力を利用することで、大容量の攻撃トラフィックも効果的に吸収・緩和できます。これにより、企業は柔軟かつ効率的にDDoS対策を実施することができます。CDN(コンテンツデリバリネットワーク)サービスを利用し攻撃を分散させるのも有効です。
高度な機械学習アルゴリズムと深層学習技術を用いて、DDoS攻撃の検知と緩和を高度化します。これらの技術は、膨大な量のネットワークトラフィックデータを分析し、通常の通信パターンを学習することで、異常を迅速かつ正確に識別します。具体的には以下のような手法が活用されています。
これらの技術により、新種の攻撃や巧妙に偽装された攻撃トラフィックも高精度で識別し、迅速に対応することが可能になります。
効果的なDDoS対策の実現には、技術的対策だけでなく、組織全体での取り組みが求められます。
DDoS対策への投資は、事業継続性の確保と顧客信頼の維持という長期的な視点が不可欠です。直接的な防御コストに加え、攻撃による潜在的な損失リスクも考慮に入れ、適切な投資レベルを決定します。
攻撃発生時の被害を最小限に抑えるため、詳細なインシデントレスポンス計画を策定します。この計画には、検知、対応、復旧のプロセスを明確に定義し、定期的な訓練を通じて計画の実効性を確認します。必要に応じて見直し、改善も行います。
企業の規模、業種、リスク特性、既存のITインフラなどを考慮し、最適なDDoS対策サービスを選択します。クラウドベースのサービスに加え、データセンターのハウジングサービスを利用した対策も効果的です。
データセンターのハウジングサービスを利用する利点は以下の通りです。
効果的なDDoS対策サービスを選択する際は、以下の点を考慮しましょう。
特に、重要な基幹システムや、常時高いパフォーマンスが求められるサービスを運用する企業にとっては、これらの要素を組み合わせた包括的なDDoS対策を検討することが重要です。自社設備とクラウドサービス、データセンターのハウジングサービスを利用することで、自社で高度なセキュリティ設備を維持するコストを抑えつつ、24時間365日の監視体制や最新の防御技術を活用することができます。
組織内の各部門(経営層、IT、セキュリティなど)と外部のセキュリティベンダーとの連携を強化します。定期的な情報交換会や合同訓練を通じて、平時から緊密な関係を築きます。これにより、インシデント発生時の迅速かつ効果的な対応が可能となります。
DDoS攻撃は年々進化し、企業にとって深刻な脅威となっています。企業を守るためには、技術的な対策だけでなく、組織全体での取り組みが不可欠です。
効果的なDDoS対策の一つとして、データセンターのハウジングサービスの活用が挙げられます。特に重要な基幹システムや高パフォーマンスが求められるオンラインサービスを運用する企業にとって、信頼性の高いデータセンターの利用は、強固な防御体制の構築に不可欠です。
さらに、多層防御戦略の採用、AIと機械学習の活用、適切な投資判断、そして緊急時の対応計画の整備が、対策の要となります。また、クラウドベースの対策サービスの活用や、専門家のサポートを受けることで、より強固な防御体制を構築できます。
DDoS対策の基盤として、システムの脆弱性を減らすことも重要です。これには、定期的なソフトウェアアップデートが不可欠です。オペレーティングシステム、アプリケーション、ファームウェアなどを最新の状態に保つことで、既知の脆弱性を修正し、攻撃に対する耐性を高めることができます。また、セキュリティパッチの適時適用や、セキュリティソフトウェアの定義ファイル更新も、効果的なDDoS対策の一部です。
急速に変化するサイバー脅威に対応するには、継続的な監視と改善が欠かせません。企業は自社のリスク特性を理解し、適切な対策を講じることで、DDoS攻撃のリスクを大幅に軽減できます。
STNetが提供する西日本最大級のデータセンター「Powerico(パワリコ)」は、JDCC最高水準の「ティア4」に準拠しており、高度なセキュリティ環境を提供しています。
さらに、クラウド型WAFサービスとして、「Scutum」サービスも提供可能です。簡単に導入でき、幅広い脆弱性に対応します。オプションの「Scutum DDoS対策プラン」はDNS切り替えだけで追加できる機能で、大規模なDDoS攻撃にも効果的に対応し企業のWebサービスを守ります。
また、STNetは包括的なセキュリティ対策として、「セキュリティ診断サービス」、セキュリティ運用監視サービス「 NetStare(ネットステア)」も提供しています。「セキュリティ診断サービス」には、サイトの脆弱性を自動診断する「デイリー自動診断」と、専門部門による詳細な「手動型セキュリティ診断」があります。これにより、サイバー攻撃のリスクを事前に特定し、対策を講じることができます。セキュリティ運用監視サービス 「NetStare (ネットステア)」は、24時間365日体制で企業のネットワークとセキュリティを監視し、インシデント発生時には迅速に対応します。これらのサービスも活用すれば、包括的なセキュリティ運用が可能です。STNetによるサービスにご興味のある企業担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。