システムバックアップとは?その重要性とスムーズに進めるための方法を解説

課題解決のためのノウハウ
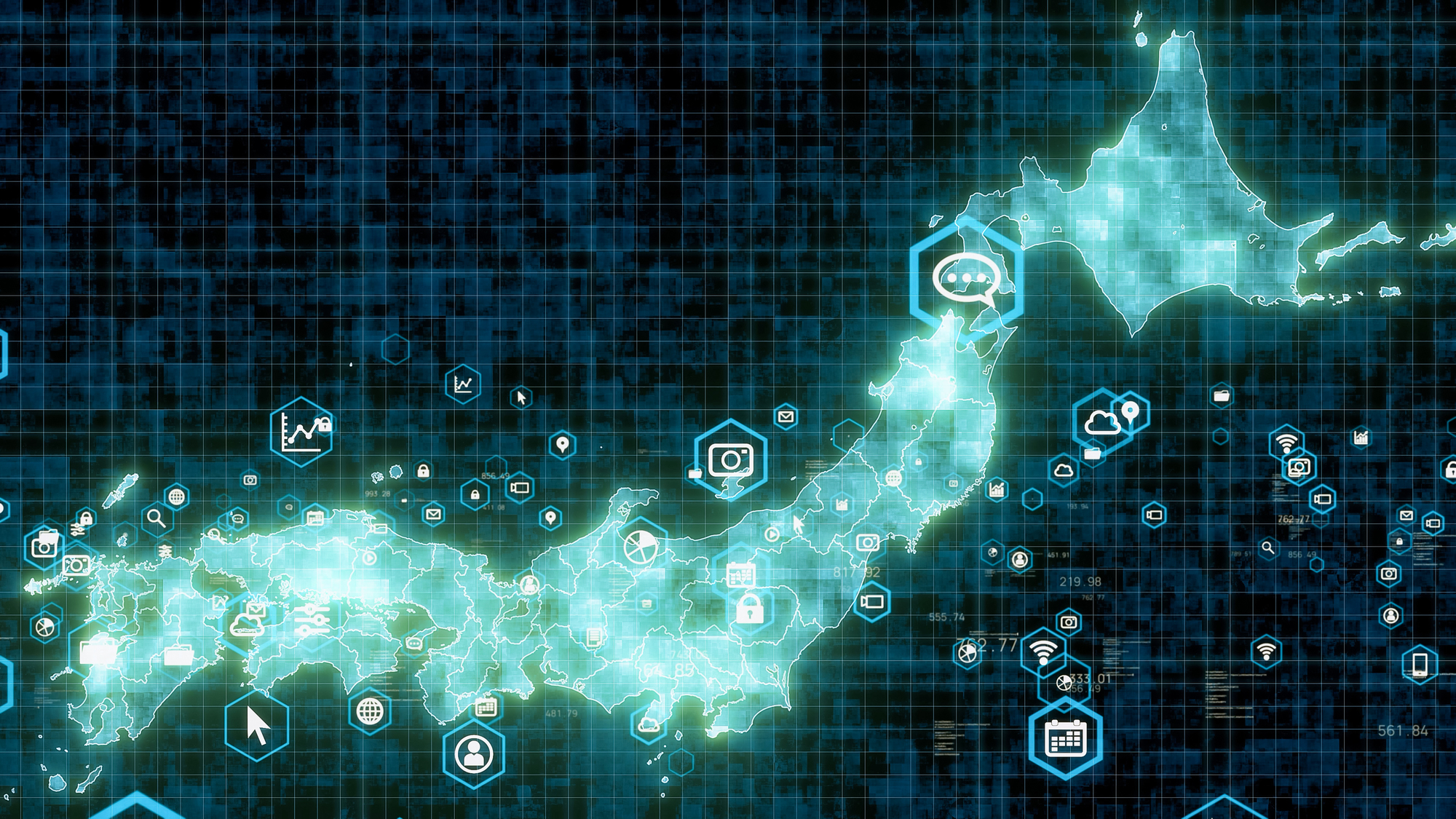
DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、企業活動におけるデータの重要性は飛躍的に高まっています。一方で、首都圏直下型地震の発生リスクや、データセンターの電力需給問題など、システム基盤を取り巻くリスクも増大しています。本記事では、地方データセンターを活用したデータの分散保管による事業継続戦略について、具体的な実現方法をご紹介します。
デジタル社会の進展に伴い、企業のデータ管理における課題が浮き彫りになってきています。
経済産業省の調査「デジタルインフラを巡る現状と課題(2021年4月)」によると、国内データセンターの約6割が首都圏に集中し、残りの多くは関西圏や北海道などの特定地域に集中しているとされています。このような地域的な偏りは、大規模災害発生時に深刻な影響をもたらす可能性があります。
特に首都圏では、電力需給の逼迫やデータセンター用地の確保が困難になってきているほか、災害発生時の同時被災リスクも高まっています。地域分散によるリスク低減は、今や経営課題の一つといえるでしょう。
参照:デジタルインフラを巡る現状と課題(2021年4月)|経済産業省
企業のDXは、コロナ禍を契機に加速度的に進展しています。基幹システムのクラウド移行やデジタルサービスの拡充により、企業が取り扱うデータ量も年々増加しています。こうしたデータは、企業の競争力を左右する「デジタル資産」であり、適切な保護と管理が必須となっているのです。
システム障害による事業停止は、想像以上に大きな損失をもたらします。NPO日本ネットワークセキュリティ協会の「インシデント損害額調査レポート第2版」では、システム停止時の損失は直接的な売上減少だけでなく、お詫び広告費用(新聞掲載等で数百万円規模)や取引先への補償、信用失墜による取引停止など、多岐にわたる影響が指摘されています。
例えば、年商50億円規模の企業におけるネットワーク停止の影響を年間ベースで試算すると、以下のようになります。
| 項目 | 平時 | 事業中断時 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 50億円 | 30億円 | ▲20億円 |
| 固定費(人件費、賃料等) | 10億円 | 10億円 | - |
| 変動費(材料費、電気代等) | 35億円 | 21億円 | 14億円 |
| 営業利益(損失) | 5億円 | ▲1億円 | ▲6億円 |
この試算例では、ネットワーク停止によって数カ月間、営業活動が制限された場合、売上高が50億円から30億円と、4割減少しています。売上高は20億円の減収となりますが、材料費等の変動費14億円の支出は抑えられるため、最終的な営業損失は6億円となっています。さらに、これに加えてシステム復旧費用やお詫び広告費用、取引先への補償等が発生するため、実質的な損失はさらに拡大する可能性があります。
また、長期の事業停止は直接的な損失以外にも、以下のような中長期的な影響をもたらすことがあります。
このように、システム停止による経営へのダメージは企業の存続にも関わる重大なリスクとなっており、データ保護体制の見直しは経営課題として捉えるべき状況となっています。
参照:インシデント損害額調査レポート第2版|NPO日本ネットワークセキュリティ協会
企業データの地方分散は、事業継続の確実性を高める施策として、多くの企業から注目を集めています。その具体的なメリットをご紹介します。
大規模災害の発生時、同一地域にデータを集中させている場合、全システムが同時に被災する可能性があります。これは事業継続の観点から大きな課題となります。
地理的分散によって得られる具体的なメリットは下記のようなものがあります。
特に地震発生頻度の低い地域にバックアップ拠点を設けることで、災害時でもデータにアクセスできる可能性を格段に高めることができます。
災害発生時の迅速な事業復旧には、DR(Disaster Recovery:災害復旧)体制の整備が欠かせません。バックアップ環境を構築することで、以下のような体制強化が可能になります。
このように、地方分散型のDR体制は、災害発生時の事業継続性を確実に高めることができます。さらに、クラウドサービスとの連携により、より柔軟で効率的な構成を実現できるようになっています。
DR体制について詳しくは、「DR対策とは?BCPに欠かせないサーバーやシステム復旧を迅速に行うための方法を解説」をご覧ください。
データの地方分散を検討する際は、地理的特性、インフラの安全性、サービス品質など、多角的な観点から適切なデータセンターを選定することが大切です。ここでは、信頼性の高いデータセンター選びのポイントを説明します。
データセンターの立地を選定する際は、地震や津波などの自然災害リスクを慎重に確認する必要があります。地盤の安定性や周辺の地形特性、プレート境界からの距離など、さまざまな要素を総合的に判断することが大切です。例えば、データセンターの分散配置を検討する際は、異なる地質構造を持つ地域を選択することで、地震リスクの効果的な低減が期待できます。
また、津波リスクについては、地形による自然の防御効果も重要な検討要素となります。内陸部や、地形的に津波の影響を受けにくい場所の選定は、自然災害に対する耐性を高める有効な手段といえます。
地域特性の評価にあたっては、歴史的な災害記録や地質調査データなども参考にしながら、総合的な災害リスク評価を行うことが推奨されます。安全性の高い立地を選定することで、データ保管拠点としての信頼性を高めることができます。
データセンターの立地について詳しくは、「データセンターの選定に場所が重要な理由とは?立地で選ぶポイントを解説」をご覧ください。
地方のデータセンターでは、大都市圏に比べて需給が安定しているとされています。経済産業省の「デジタルインフラを巡る現状と課題」によると、首都圏ではデータセンターの電力消費増加に伴い、需給の逼迫が課題となっており、安定した電力供給が求められています。一方、地方では再生可能エネルギーの活用が進んでおり、地域によっては電力供給の安定性を確保するための施策が展開されています。加えて、総務省の『データセンターの地方分散の推進に関する調査報告書(2022年3月)』では、地方データセンターは大都市圏に比べて電力供給が安定しやすく、災害時の電力確保も容易である可能性が示唆されています。また、地域による電力コストの違いも、運用面での優位性となり得ます。
一方で、近年のAI開発やビッグデータ処理の需要増加により、データセンターの消費電力量は急増しています。特に首都圏や北海道など、特定地域への高負荷データセンターの集中は、経済産業省の「第6次エネルギー基本計画」においても電力需給の逼迫要因として言及されており、今後のエネルギーインフラの整備状況が重要になるとされています。将来的な電力インフラの整備状況も含めて検討することが賢明でしょう。
冗長化された高速ネットワーク回線の採用により、安定したデータ通信を実現していることも選択条件の一つです。さらに、災害時のバックアップ回線確保など、通信経路の多重化により、高い可用性を担保していることも必要です。加えて、24時間365日のネットワーク監視体制による通信品質の維持管理も、データセンター選定の大切なチェックポイントとなります。障害発生時には迅速な切り替え対応が可能な体制を整えることで、安定したサービス提供を実現できるでしょう。
システム運用の効率化を実現する充実したマネージドサービスの提供も、必要な選定条件の一つです。システム監視や運用代行、障害対応など、企業のニーズに応じた柔軟なサポート体制を整備していることが求められます。特に、電話一本で必要な作業を依頼できる作業代行の体制なども、企業の運用負荷の軽減とセキュリティ品質の向上を両立します。24時間365日の障害受付体制や、迅速な一次対応、さらには障害原因の調査・報告まで、包括的なサポート体制を確認することで、より安心なデータ運用が可能となります。
これらの条件を総合的に検討し、自社に最適なデータセンターを選定することで、効果的なデータ分散が実現できるのです。
データセンターを選定する際に失敗しないポイントについては、お役立ち資料「失敗しないデータセンター選び 5つのポイント」もダウンロードしてご覧ください。
データの地方分散を成功させるには、現状分析から導入・運用開始まで、計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、成功に導くための具体的なステップを紹介します。
データの地方分散は、まず、事業継続に関わるデータの棚卸しから始めます。基幹システムのデータベース、顧客情報、経理データなど、業務の優先度に応じてデータを分類します。
この段階で明確にすべき具体的な要件には、以下のような項目があります。
これらの要件を明確にすることで、次のステップでの具体的な分散構成パターンの検討がスムーズになります。
データ保護の手法は、データセンターハウジング、クラウドサービス、自社施設内設置(オンプレミス)など、複数の選択肢があります。データの特性や予算に応じて、これらを組み合わせたハイブリッド構成という選択肢もあります。
特にデータセンターハウジングは、以下の点で理想的なソリューションといえます。
実運用を見据えた具体的な検討項目として、以下の項目を決定します。
特にリカバリ時間については、事前の検証を重ね、想定したタイムラインでの復旧が可能か確認することが望ましいでしょう。この検証結果に基づき、必要に応じて運用設計の見直しを行います。
システムのバックアップについて詳しくは、「システムバックアップとは?その重要性とスムーズに進めるための方法を解説」をご覧ください。
一度にすべてのデータを移行するのではなく、優先度の高いものから段階的に進めることが推奨されます。具体的には、以下の手順で進めていくことをおすすめします。
このように段階的に進めることで、移行に伴うリスクを最小限に抑えながら、確実なデータ分散を実現できるでしょう。
データの地方分散は、一朝一夕には実現できません。しかし、これらのステップを着実に進めることで、信頼性の高い事業継続体制を構築できます。
デジタル社会の進展に伴い、企業活動におけるデータは事業継続の要となっています。そして、大規模災害や電力需給の逼迫などのリスクに備えるため、データの地方分散による事業継続体制の構築が急務となっているのです。その実現に向けて、データ分散先の選定においては、地震・津波リスクの低さ、電力供給の安定性、ネットワークの信頼性、運用サポート体制など、多角的な視点での検討が必要です。
四国・香川県に立地するSTNetのデータセンター「Powerico(パワリコ)」は、瀬戸内海沿岸部の地理的特性を活かした、自然災害に対する高い安全性を備えています。最大定格21KVAの安定した電力供給、信頼性の高い冗長化されたネットワーク環境、24時間365日の運用監視体制を実現しています。さらに、電話一本で必要な作業を依頼できるリモートハンズサービスなど、充実したマネージドサービスにより、お客さまの大切なデータを保護します。
事業継続体制の強化に向けて、データバックアップやDR、基幹システムの運用など、さまざまなニーズに対応可能です。データの地方分散による事業継続体制の構築をご検討中のお客さまは、ぜひお気軽にSTNetにご相談ください。