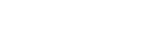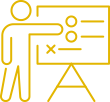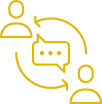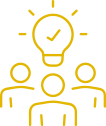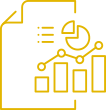case study
取り組み事例
一般財団法人 阪大微生物病研究会

仲間を思い、デザインシンキングで
たどり着いた解決策とは?
一般財団法人阪大微生物病研究会(BIKEN財団)は、「優れたワクチンを通じて、世界中の人々の大切な命を守る」をミッションに掲げ、主にワクチンの研究開発から製造までを行う、日本を代表するワクチンメーカーです。大阪に財団本部、香川県の観音寺研究所に製造拠点を置き、事業を展開しています。
今回SoCoラボでのワークショップに参加した経緯や効果、現在の取り組み状況について、経営企画部システム課の佐々木課長、高津主任に伺いました。
-
一人情シスの働く環境を
デザインシンキングで
少しでも良くしたい設立したばかりのSoCoラボの取り組みを知った佐々木課長は、「デジタルで新たな価値を創造し、四国の豊かな未来をつくる」というビジョンに共感し、何か一緒にやってみようとワークショップへの参加を決めました。とはいえ、SoCoラボの掲げる「デザインシンキング」というアプローチは経験もなく、どのような結果が出せるのか不安も大きかったと言います。
デザインシンキングはテーマ設定が肝心で、従来の仮説検証型アプローチと違い、まだ明確な課題になっていない、ぼんやりとした悩みごとをテーマに設定することが特徴。そこで、SoCoラボからの助言も得ながら、かねてから気にかけていた、財団本部で一人奮闘するシステム課員の働く環境を取り上げました。
システム課ではBIKENグループ内からの質問や相談に対応していますが、件数が多く、その内容も幅広いにも関わらず、財団本部の課員は一人だけ。問い合わせは対面のほか、電話・メール・SNSでも寄せられます。それらを通常業務と並行して対応する日常は苦労も多いだろうと感じていました。そこでデザインシンキングを活用して、その状況を皆で話し合う場を持とうと考えたのです。
(左)経営企画部システム課 高津主任/(右)経営企画部システム課 佐々木課長
-
業務への取り組み姿勢を
振り返るきっかけにもデザインシンキングに対して、佐々木課長は別の期待も持っていました。そもそもシステム課は、従業員にITサービスを提供する部署。利用する従業員のよりよい環境を目指すのが本来の姿です。しかし、つい自分たちの合理性を優先してしまう場面も。そこで、ペルソナに共感して解決策を導くデザインシンキングは、相手のことを深く思い考えるきっかけとなり、今後の仕事にも役立つのではないかと。また、職場から離れた空間での共同作業となるので、予期しない発見や変化があれば面白いなとも考えていました。
SoCoラボ課題探求・解決ワークショップの
流れ-
検討テーマの選定
事前に相談し「どうすれば離れた拠点にいる一人情シスがワクワクしながら仕事ができるか」をテーマに選定した。
-
理解・共感・課題発見
一人情シスとなっている課員をペルソナ(幸せにしたい対象)に設定し、ペルソナに共感しながら「問い合わせ業務」に焦点を当てて課題を探った。
-
解決策のアイデア創出
発見した課題を解決すべく、従業員(業務ユーザー)に問い合わせルールを順守してもらうための意見を出し合い、アイデアスケッチにまとめた。
-
アイデアの優先順位付け・見える化
複数作成したアイデアスケッチから優先度の高いものを選定し、ユースケース「問い合わせ窓口の整備に向けたチャットボット導入」を作成した。
-
PoC計画
チャットボット導入の効果を実証するためのPoC計画(アイデアの実現可能性や効果を検証するための計画)を作成した。
SoCoラボの役割:助言およびファシリテート
-
-
参加者同士の距離が縮まり
チームの一体感が向上ワークショップ中は常に主体的に考えることが求められ、SoCoラボの非日常的な空間も相まって「時間の経過を忘れるほど充実した時間だった」と二人は振り返ります。
はじめに参加メンバー6人でテーマを再認識。「どうすれば離れた拠点にいる一人情シスがワクワクしながら仕事ができるか」と、悩みごとをポジティブな言葉に置き換えて、SoCoラボのファシリテートによるワークショップがスタートしました。
今回のワークショップでは、実在する一人をペルソナに設定し、本人もワークショップに参加する方法を採りました。
そのため、悩みごとに対する共感がより具体化したり、意外な一面を知り互いの距離が縮まったりという効果もありました。
なかでもメンバーのチームワーク向上に大きく影響したのが、一人一人が絵で表現した課題解決のためのアイデアスケッチ。もともとデザインシンキングにおいては、絵で表現することにより共通認識が深まり、アイデアのブラッシュアップにつながるという効果があります。それ以上に、全員で見せ合った手描きの絵で盛り上がり、通常業務では見られない瞬間や、個々の能力を共有することで関係性がよくなる効果も生まれました。さらにブラッシュアップを重ね、最終的に「問い合わせ業務の負担を軽減するチャットボットを導入する」という解決策を導き出しました。
-
解決策にたどり着くまでの
プロセスに価値がある「もし誰か一人に同じテーマで解決策を考えてもらったら、今回と近い話が出てくる可能性はあるでしょう。しかし、6人のメンバーがペルソナの行動・思考・感情までをシナリオに落とし込んで辿り着いた解決策には圧倒的な説得力と、すぐに皆で実行できるモチベーションが伴っています」と佐々木課長。
「これはデザインシンキングのプロセスによって生み出された効果。その体験から新たな活用シーンとして『新規案件スタートアップ時のチームビルディングに』といったイメージもできるようになった」と佐々木課長は振り返ります。
「もちろんデザインシンキングのアプローチはすべてに有効だとは言えません。しかし今の時代、仮説検証型アプローチだけでは組織的にスピーディーにイノベーションを生み出すのは難しい。そういうときこそ、デザインシンキングの本質的な価値が見出せるのではないか」と高津主任は考えています。
-
試しながらの分析と改善で
好循環を生み出したいワークショップの後、よくある問い合わせ内容とその回答をチャットボットに登録することで、グループ内の問い合わせをチャットボットが回答する仕組みを導入しました。試行運用で期待する効果が得られるか検証した上で、本格運用に移行。ちょうど他の部署からも相談があり、人事、経理、経営企画を加えた計4部署で導入しています。
「例えば、グループポータルサイトに『各部署からのお知らせ』や各種規程、マニュアル類が掲示されていますが、情報量が多いため探索が難しい状況です。しかし、チャットボットにいつでも気兼ねなく質問できるようになり、まずはユーザーとして便利さを実感しました」と高津主任。
問い合わせ業務にも改善の効果が表れました。チャットボットには毎月300件超の問い合わせがありますが、そのうち50%が「チャットボットの回答で満足した」という結果が出ています。それまでの問い合わせ業務の負担軽減となり、導入コストと比較しても価値があると判断しています。
「現在は定期的に問い合わせ内容と回答率を分析し、回答を充実させる活動を続けています。今後さらに導入部署が増え効果も上がるという好循環に繋げていきたい」高津主任と語ってくれました。Point
 一人のシステム課員に集中していた問い合わせ業務の負担軽減をきっかけに、問い合わせ窓口の整備に向けたチャットボットを導入
一人のシステム課員に集中していた問い合わせ業務の負担軽減をきっかけに、問い合わせ窓口の整備に向けたチャットボットを導入
毎月300件超の問合せ業務の半数がチャットボット内で解決 ユーザーに共感してプロセスを進めるSoCoラボワークショップでは、圧倒的な説得力を持つ解決策とすぐに実行できるモチベーションが得られる
ユーザーに共感してプロセスを進めるSoCoラボワークショップでは、圧倒的な説得力を持つ解決策とすぐに実行できるモチベーションが得られる 第三者によるファシリテート、そして普段の職場を離れた非日常空間で集中的に議論することは、更なる共通理解を築き、メンバー間の関係性を向上させる貴重な機会となる
第三者によるファシリテート、そして普段の職場を離れた非日常空間で集中的に議論することは、更なる共通理解を築き、メンバー間の関係性を向上させる貴重な機会となる
※掲載内容は、取材当時(2023年9月)のものです。
INFORMATION

一般財団法人 阪大微生物病研究会
- 所在地
- 大阪府吹田市山田丘3番1号 大阪大学内
- 設立
- 1934年6月6日
- 事業内容
- ワクチンの研究・開発・供給、検査、学術助成
Contact
また、フォームからもお問い合わせいただけます。